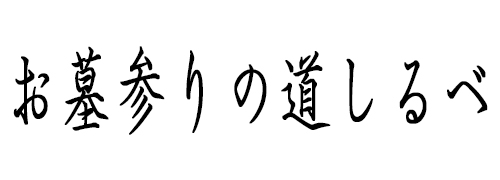数珠(じゅず)は仏教徒にとって最も身近な仏具のひとつです。しかし宗派によって形や使い方が異なるため、いざ葬儀や法事で使おうとすると「どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いでしょう。
本記事では、数珠の基礎知識から宗派ごとの違い、略式数珠の選び方、用途別の選択ポイント、正しい使い方やお手入れ方法まで、初めての方でも安心して選べるよう丁寧に解説します。
結論:宗派に合った数珠を選ぶのが理想。ただし初心者は略式数珠から始めるのも安心。大切なのは敬意を持って丁寧に扱う心です。
略式数珠(片手数珠)という選択肢
初心者の方はまず「略式数珠(片手数珠)」から始めるのがおすすめです。
- 特徴:宗派を問わず誰でも使える汎用型
- 珠の数:約108玉の代用(27玉・54玉など)
- サイズ:コンパクトで携帯しやすい
- 価格帯:5千円〜2万円程度が主流
- 用途:葬儀・法事・お墓参り・日常の礼拝まで幅広く使える
※実際のお墓参りでの使い方や作法はこちらで詳しく解説しています。
お墓参りの基本完全ガイド|初めてでも安心の準備・作法・持ち物・服装まで
宗派別の正式な数珠の特徴と選び方
宗派に合わせた正式な本式数珠は、それぞれの教義や作法を反映した形になっています。
浄土真宗
- 親珠:2つ(阿弥陀如来と親鸞聖人)
- 材質:黒檀・紫檀・白檀
- 房の色:茶・白
- 使用サイズ:
- 普段使い:8寸
- 法要用:10寸
仏壇屋 滝田商店 数珠 浄土真宗 本式数珠 【男性用】黒ビルマ翡翠 22玉 正絹紐房◆京念珠・本連数珠・二輪数珠・門徒・正式数珠【滝田商店発行 京念珠製造師製作証明書付】
Amazonで見る
曹洞宗
- 親珠:1つ
- 材質:黒檀・青檀
- 房の色:黒・濃茶
念珠ドットコム ≪ペア数珠≫曹洞宗 数珠 男性用(尺二 青虎目石 本銀輪 紐房)・曹洞宗 数珠 女性用(8寸 淡水パール 本水晶 本銀輪 正絹房)ペアセット【本式数珠 京念珠 京都 禅宗 二連 二重 二輪 葬儀 ギフト マイ数珠 2000500100789】【数珠袋プレゼント!】
Amazonで見る
天台宗
- 親珠:1つ(大きめ)
- 材質:紫檀・白檀
- 房の色:深紫色
≪特別価格≫念珠ドットコム 天台宗 数珠 男性用 9寸 紫檀(艶消し) 梵天房【本式数珠 京念珠 108玉 京都 朱丹 したん 九寸 葬式 葬儀 法事 法要 マイ数珠 2000300700264】【数珠袋プレゼント!】
Amazonで見る
真言宗
- 五色の房(五智如来の象徴)
- 親珠:金剛杵型
- 材質:天然木・水晶
仏壇屋 滝田商店 数珠 真言宗 本式数珠 女性用 紫水晶 グラデーション 8寸 正絹華梵天房◆ 京念珠・本連数珠・二輪数珠・振分・正式数珠 【滝田商店発行 京念珠製造師製作証明書付】
Amazonで見る
価格帯別のおすすめ
1万円未満(入門向け)
仏壇屋 滝田商店 京念珠 数珠 男性用 青虎目石 22玉 正絹頭付房 数珠袋付き すべての宗派で使える男物念珠 証明書付
Amazonで見る
1〜3万円(一般的な品質)
福正堂 数珠 念珠 男性用 【葬祭プロ監修 京都伝統工芸品】 葬儀 葬式 じゅじゅ 略式数珠 男性 金黒曜石
Amazonで見る
3万円以上(高級・職人製作)
仏壇屋 滝田商店 京念珠 数珠 男性用 インド白檀 20玉 正絹頭付房 数珠袋付き すべての宗派で使える男物念珠 証明書付
Amazonで見る
葬儀・法事での数珠の正しい使い方
- 合掌時:両手にかけ房を垂らす
- 焼香時:左手首にかけ右手で焼香
- 床に置かない・揺らさない・絡めない
数珠のお手入れと保管方法
- 使用後は専用袋へ
- 乾拭きで清掃
- 湿気・直射日光を避ける
- 房の絡まり防止
- 糸切れは専門店で修理
数珠と宗派の祈りの関係
数珠の使い方は各宗派の祈りと深く結びついています。
実際のお経や念仏の違いについては、こちらで詳しく解説しています。
お経と念仏の違いを徹底解説|仏教の基本から現代の実践までわかりやすく解説
世界の数珠文化とのつながり
数珠は仏教だけでなく、世界中の宗教文化でも共通して使われています。
その起源や各宗教での役割はこちらで紹介しています。
数珠は仏教以外でも使うの?世界の数珠文化を徹底解説
レオビ- ストア LEOBEE 数珠 男性用 縞黒檀(艶消) マグネット式数珠袋付き 念珠 じゅず 葬式 葬儀 墓参り 法事 念誦 全ての宗派に使用可能
Amazonで見る