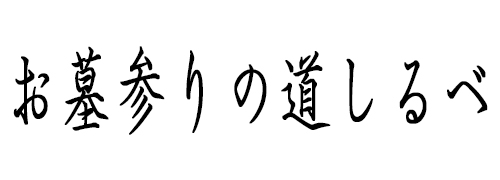鳥居といえば「神社の入り口」というイメージが一般的です。
ところが実際には、お寺でも鳥居を見かけることがあります。
「お寺なのに鳥居?」と疑問に思った経験のある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、鳥居の本来の意味・お寺に鳥居がある歴史的背景・実例・正しいお参りの仕方まで、仏教学と民俗学の視点からわかりやすく解説します。
結論:鳥居は神社の象徴であると同時に、神仏習合の名残としてお寺でも見ることがある日本独自の信仰文化です。
1. そもそも鳥居とは?基本をおさらい
鳥居の本来の役割
- 神社における神域と俗世を区切る結界
- 鳥居をくぐることで「聖なる空間に入る」意識を持つ
- 構造はシンプルながら深い意味を持つ日本固有の建造物
主な鳥居の種類
- 神明鳥居(しんめいとりい)
最も古い様式。まっすぐな木材で構成される簡素な形 - 明神鳥居(みょうじんとりい)
笠木(上部)が反り返った優美な形。多くの神社で採用
2. お寺に鳥居があるのはなぜ?
神仏習合という日本独自の宗教融合
- 神仏習合(しんぶつしゅうごう):仏教と神道が長年共存・融合してきた日本の信仰形態
- 奈良時代以降、寺院と神社が同じ敷地内に存在するケースが普通だった
- 神社の中に仏堂、お寺の中に鎮守社が併設されることも多かった
明治の神仏分離まで続いた文化
- 明治政府による神仏分離令(1868年)以前は「神も仏も同時に祀る」ことが広く行われていた
- 現在でも神仏習合の名残として、お寺に鳥居が残っているケースがある
鳥居=神社の専売特許ではない理由
- 鳥居はあくまで「神域の入口」であり、必ずしも建物の種類(神社 or 寺院)に限定されない
- お寺の境内に祀られた神様(鎮守神)の前に鳥居が残される例が今も各地に存在する
3. 実際に鳥居が残る有名な寺院の例
| 寺院名 | 所在地 | 鳥居の背景 |
|---|---|---|
| 比叡山延暦寺 | 滋賀県大津市 | 鎮守社「日吉大社」との深い結びつき |
| 長谷寺 | 奈良県桜井市 | 境内に「天満宮」を祀り鳥居が存在 |
| 四天王寺 | 大阪府大阪市 | 聖徳太子創建、神仏習合の色濃い歴史 |
私も修行時代、比叡山で鳥居のあるお堂を訪れたことがありますが、「お寺なのに鳥居」という違和感は感じず、むしろ自然な神仏の共存を体感できた思い出があります。
4. お寺の鳥居でのお参りマナーは?
参拝先で作法が変わる
| 参拝先 | 作法 |
|---|---|
| 鳥居の先が神社(鎮守社)の場合 | 神社式(軽く一礼→二礼二拍手一礼) |
| 本堂など仏教施設の場合 | 仏教式(合掌→一礼) |
※ 境内案内板や祭神案内が設置されている場合はそれを参考にしましょう。
焦らなくて大丈夫
- お彼岸・お盆などのお墓参りに来た際に、お寺で鳥居を見つけても戸惑わず、「神仏習合の名残だな」と受け止めればOKです。
5. 鳥居の背景にある神仏観の違い
| 信仰体系 | 役割 |
|---|---|
| 神道 | 神々の世界との結界 |
| 仏教 | 本来は鳥居を使わないが、守護神(鎮守)を祀る時に併設される |
→ 日本人は長く 「神も仏も共に敬う柔軟な信仰文化」 を自然に受け入れてきました。
6. 関連記事で理解をさらに深める
まとめ
鳥居=神社というイメージは正しくはあるものの、日本の宗教文化はもっと柔軟で奥深いものです。
神仏習合の歴史を知ることで、お寺にある鳥居も決して不思議ではなく、むしろ日本の信仰の豊かさを象徴する存在であることがわかります。
これからお寺参拝をする際には、ぜひ鳥居の有無にも注目してみてください。
そこには長い歴史の名残が静かに息づいているかもしれません。
今さら聞けない神社とお寺の違い エイムック
Amazonで見る