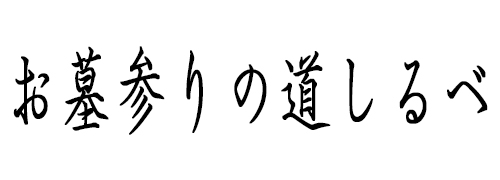お盆やお彼岸の供養で悩みやすいのが「お供え物」。
何を選べばよいのか?マナーはあるのか?──そんな疑問に仏教・民俗学を学んだ筆者がわかりやすくお答えします。
宗派や現代のライフスタイルもふまえて、迷わず準備できる実用ガイドです。
結論:故人を想う心を大切に、季節感・衛生面・宗派の特徴に配慮して選べば大丈夫です。
基本のお供え物|まずはここを押さえよう
1. 果物
- 季節のフルーツが喜ばれる(例:スイカ・桃・ぶどう・梨 など)
- 新鮮なものを選び、傷や痛みは避ける
2. お菓子
- ようかん・まんじゅう・せんべい・ゼリーなど
- 家族で分けていただきやすい個包装が便利
とらや 小形羊羹 10本入
Amazonで見る
3. 野菜
- お盆なら精霊馬(きゅうり馬・なす牛)を作る地域も
- 精進料理に使われる食材も供え物に適す
4. 飲み物
- お茶・水・お酒(故人が好んだものを)
5. お花
- 仏花(菊・リンドウ・ユリなど)
- 棘のあるバラ・毒を持つ花は避けるのが通例
宗派・地域による注意点
- 浄土真宗など一部宗派は「供物の儀式性よりも心が大切」とする考え方あり
- 真言宗では「三種供物」を重視(菓子・果物・花)
- 地域独自の風習例:山形では「精進そうめん」のお供え
※迷った場合は、菩提寺の住職に確認すると安心です。
季節感を大切に選ぶ
- 春彼岸(3月頃):イチゴ・デコポン・桜餅など
- お盆(8月頃):スイカ・ぶどう・桃・冷菓など
- 秋彼岸(9月頃):梨・柿・栗・おはぎなど
旬のものを選ぶことで、より丁寧な心が伝わります。
意外と知らないお供えマナーと注意点
① 生ものは避けよう
- お寿司・刺身は腐敗が早いため避けるのが無難
- どうしても好物を供えたい場合は「お寿司型和菓子」などの代用品も可
② 数は奇数が縁起良し
- 3個・5個などの奇数で並べるのが一般的
- 真言宗では「三種供物」の三を重視する慣習も
③ 割れ物・傷物は避ける
- ヒビや欠けのある器やせんべいは避ける
- 果物も傷のない美品を選ぶ
現代生活に合わせた新しい配慮
① 忙しい方の時短供養
- 毎日立派に揃えなくても、水やお茶だけの日も大切
- 簡素でも「毎日手を合わせる習慣」が一番の供養
② アレルギー・嗜好配慮
- 小麦・ナッツなどの除去品を選ぶ配慮
- ベジタリアン・ヴィーガン向けに植物性中心のお供えも
③ エコフレンドリー供養
- 使い捨て容器を減らす
- 地元食材の活用、簡易包装の採用なども供養の心遣い
よくあるQ&A
Q1:お供え物はどれくらい置く?
A1:基本は半日〜1日以内。生花や果物は3日程度を目安に交換。
Q2:お供えの並べ方は?
A2:一般的に、故人に向かって右に食べ物、左に飲み物。ただし宗派差あり。
Q3:お金を供えてもいい?
A3:通常は行いませんが、法要の際のお布施・志は別です。祭壇に直接お金を置くことは避けます。
まとめ:供養の本質は「心を込めること」
お盆やお彼岸は、形式ではなく「故人を想う心」を表す行事です。
供え物を選ぶ過程そのものが、亡き人との心の対話となります。
私自身、厳格な作法にこだわっていた修行時代を経て、今は「自然体の供養」を大切にしています。
今年は何を供えようかと家族で話し合う、その会話もまた故人への供養の一部なのです。