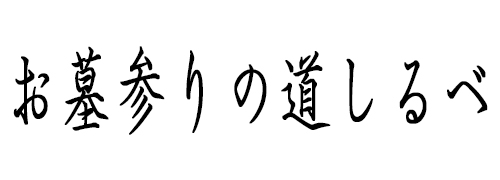お彼岸とお盆──どちらも先祖を敬う大切な行事ですが、具体的な違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、時期・意味・由来・過ごし方をやさしく整理しながら、現代の供養スタイルの変化も含めて詳しく解説します。
結論:お彼岸は「春分・秋分に先祖と悟りを意識する行事」、お盆は「先祖の霊を迎え、もてなす行事」。ともに先祖への感謝の心が中心です。
お彼岸とは?|太陽の動きと悟りの世界
お彼岸の時期
- 春のお彼岸:春分の日(3月20日〜21日頃)を中心に前後3日、計7日間
- 秋のお彼岸:秋分の日(9月22日〜23日頃)を中心に前後3日、計7日間
- 彼岸の中日:春分・秋分当日
※地域や寺院によって細かな差もあります。
お彼岸の由来・意味
- 語源:「彼岸(ひがん)」=仏教で「悟りの世界・極楽浄土」
- 春分・秋分は太陽が真東から昇り、真西に沈む → 西方浄土を象徴
- 此岸(しがん)=現世 → 彼岸(ひがん)=悟りの世界へ至ることを願う期間
お彼岸の過ごし方
- お墓参り
- 仏壇へのお供え(おはぎ・ぼたもち)
- お経・読経
- 先祖を偲び、感謝の気持ちを表す
お盆とは?|先祖の霊をお迎えする行事
お盆の時期
- 新暦(多くの地域):8月13日〜16日
- 旧暦(東京・一部地域):7月15日前後
※地域によって時期が異なります。
お盆の由来・意味
- 起源は仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)
- サンスクリット語の「ウラバンナ」(倒懸:逆さ吊りの苦しみを救う)に由来
- 釈迦の弟子・目連尊者が亡母を救った説話から発展
- 日本では祖霊信仰と融合し「先祖の霊が里帰りする期間」として定着
お盆の過ごし方
- お墓掃除・墓参り
- 精霊棚・盆提灯の準備
- 迎え火・送り火
- 精霊馬(きゅうり馬・なす牛)
- 盆踊り
- お供え物(果物・野菜・菓子など)
お彼岸とお盆の違いまとめ表
| 比較項目 | お彼岸 | お盆 |
|---|---|---|
| 時期 | 春分・秋分(年2回) | 夏の13日〜16日(年1回) |
| 由来 | 西方浄土信仰・悟りを願う | 盂蘭盆会(祖霊信仰と融合) |
| 主目的 | 先祖供養+自身の徳積み | 先祖の霊を迎えもてなす |
| 食べ物 | おはぎ・ぼたもち | 精進料理・果物・お菓子 |
| 行事内容 | お墓参り・法要 | 精霊棚・盆踊り・迎え火 |
現代社会における変化と新たな供養スタイル
- 核家族化・遠方化 → 墓参り困難 → 自宅供養・永代供養の選択も
- 墓じまい・樹木葬・散骨の普及
- SNS供養・オンライン法要の登場
- お彼岸・お盆に縛られず日常的に供養する家族も増加
家族の形が多様化する中でも「感謝と祈りの心」は今も変わらず続いています。
関連記事でお墓参りの実践も確認
- お墓参りの基本完全ガイド|初めてでも安心の準備・作法・持ち物・服装まで
- お墓参りの基本的な手順とマナー|初心者でも安心の完全ガイド
- お墓参りに準備するもの完全リスト|初心者でも忘れ物ゼロ
- 人はなぜお墓参りをするのか?その意義を徹底解説
- 数珠の選び方完全ガイド|宗派別の特徴と選び方を徹底解説
とらや 小形羊羹 10本入
Amazonで見る