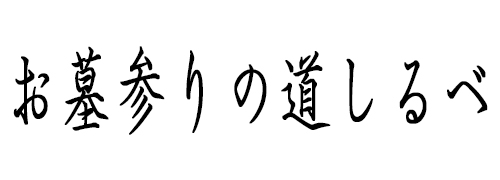お墓参りやお仏壇に手を合わせるとき、何気なく手に取る「仏花(ぶっか)」。でも、「なぜお花を供えるの?」「決まった種類があるの?」「神社では使わないの?」といった疑問を抱いたことはありませんか?
この記事では、仏花の意味や歴史、宗教ごとの違い、現代での考え方までをやさしく丁寧に解説します。読めば、お供えの花に込められた深い思いを知り、これからのお墓参りや供養の時間がもっと心のこもったものになるはずです。
仏花とは、亡くなった方への供養や感謝の気持ちを込めて仏前に供える花のことで、仏教に基づく風習ですが、民間信仰や現代の生活習慣にも広く根づいています。
仏花とは?なぜお供えするのか
仏花とは、仏壇やお墓、法事などで仏さまやご先祖にお供えするための花のことです。単なる飾りではなく、以下のような意味が込められています。
- 敬意と感謝の表現
- 仏や故人に対する尊敬の念
- 生前の感謝の気持ちを込めて
- 無常をあらわす象徴
- 花は咲いてやがて枯れるもの
- 仏教では「諸行無常(すべてのものは変化する)」の教えと重なる
- 清浄のしるし
- 花の香りや彩りには空間を清める意味合いもあるとされます
特に四十九日や一周忌などの節目には、花を通じて想いを届けることが仏教行事の一環とされています。
仏花は誰が決めた?その由来と歴史
仏花の習慣は、インドの仏教伝来とともに中国・日本へと伝わってきました。もともと釈迦(しゃか)が生きていた時代、信者たちは香や灯明(とうみょう)とともに花を捧げていたとされます。
日本においては奈良時代以降、貴族や僧侶の間で仏前に花を供える習慣が広まり、やがて一般庶民にも浸透。江戸時代には「仏花」という言葉が文献にも見られるようになりました。
明確に「仏花はこうあるべき」と決めた人物がいるわけではなく、時代や宗派、人々の暮らしの中で自然に形づくられてきた文化なのです。
仏花に向いている花・避けるべき花
仏花には、見た目の美しさだけでなく、意味や日持ちの観点から選ばれることが多いです。
向いている花の例
- 菊(長持ちし、邪気を払うとされる)
- カーネーション(柔らかく優しい印象)
- グラジオラス(立ち姿がよく、格調高い)
- リンドウ(仏教行事によく用いられる)
- ユリ(浄化や慈しみを象徴)
避けるべき花の例
- トゲのある花(バラなど):攻撃性を連想させるため
- 香りが強すぎる花(ユリを除く):不快感を与える場合も
- 毒性のある花(スイセンなど)
とはいえ、地域や宗派、故人の好みによってはこうしたルールにこだわらず、思いのこもった花を選ぶケースもあります。
神社では仏花を使うの?
神社は神道の場であり、本来「仏花」という言い方は使いません。神道では、神棚やお墓にお供えする花を「神花(しんか)」と呼ぶこともあります。
ただし、実際には神社の境内にある墓地や、神道式のお葬式でも花を供える習慣があるため、見た目には仏花と区別がつかないこともあります。
詳しくはこちらの記事も参考になります:
お墓はお寺にしかない?神社のお墓の歴史と現代の実態を徹底解説
宗派による違いはあるの?
仏教の宗派によって、仏花の考え方や使い方には多少の違いがあります。
浄土真宗
- 「故人はすでに仏になっている」という考えから、あまり花にこだわらず、形式よりも思いを重視する傾向があります。
曹洞宗・臨済宗
- 供花は左右対称に、整然と供えるのが基本とされます。
- 花器の置き方や花の色にも細かい作法があることも。
日蓮宗
- 葬儀では五色の供花を使うこともあります(五大や五仏を表現)。
宗派ごとの儀礼に従うのが理想ですが、一般家庭では「常識的な仏花」であればとがめられることはほとんどありません。
関連記事:
数珠の選び方完全ガイド|お寺と神社での使い分けから葬儀での作法まで徹底解説
よくある誤解と注意点
- 「どんな花でもよい」は本当?
- 心がこもっていれば何でもいいという考えもありますが、葬儀や法事ではある程度の常識が求められます。
- 「花は1本でもOK?」
- 個人のお参りでは問題ありませんが、法事などの場では一対(2束)で供えるのが一般的です。
- 「造花でもいいの?」
- 墓地では風雨による劣化を防ぐため、近年は造花を用いる人も増えています。ただし、寺院によっては生花を推奨するところも。
豆知識:仏花と民俗信仰の関係
地域によっては、仏花に特定の植物を使う慣習が残っています。たとえば、
- 長野や新潟では「しきみ(樒)」を用いるのが一般的
- 沖縄では鮮やかな色の花束で故人をにぎやかに送り出す文化も
これは、仏教と民俗信仰が融合した日本独自の供養文化の一端といえるでしょう。
まとめ
仏花は、ただの飾りではありません。そこには「感謝」「敬意」「清浄」「無常」といった、仏教の教えや人々の想いが込められています。宗派や地域、時代によっても形は変わりますが、大切なのは「相手を想う気持ち」。
これから仏花を手に取るとき、ふとその背景にある意味に思いをはせていただけたらと思います。
お墓参りや供養についてもっと知りたい方は、こちらもぜひご覧ください:
お墓参りの基本的な手順とマナー|初心者でも安心の完全ガイド
人はなぜお墓参りをするのか?その意義を徹底解説
アイメディア(Aimedia) お墓・仏壇用 お供え花 2束組 造花 仏花 墓花 榊 神棚 長持ち お墓参り お盆 お彼岸 慶弔 高さ45cm
Amazonで見る